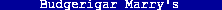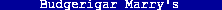| |
最初に手に入れたオシロスコープは高校生の頃に
買ったもので、真空管式の中古でリーダー電子ものでした。
型名は記憶にありません。外装は灰青色、5インチ
CRTだったと思います。時代的にはトリオのCO-75あたり
と同世代だと思います。当時のトリオ現行品は、
たぶんCS-1570系の後継であるCS-1820系だと思われますから、
当時において15〜20年落ちのポンコツです。
遅延掃引どころか、トリガ掃引すら付いていない、
単現象、5MHzのものでした。
雑誌の広告を見て通販で購入し「チッキ」(死語)で送って
もらったのでした。
今のように宅配便がなかった当時、国鉄貨物が「駅留め」と
称して個人向け荷物の運送を担っていました。
トリガ掃引がないので、波形を静止して観測するには、
手動で掃引周波数つまみを操作しなければなりません。
掃引用ののこぎり波はサイラトロン管(TY-66G-MT)で
生成していたと思います。周波数を可変すると、十数kHzの
あたりでキリキリキューンと小さな振動音が聞こえるものでした。
連続波ならこの方法でどうにか表示できますが、
単発波形などは無理でした。
当時中古で3,000円でした。今の貨幣価値にすると、
1万円ぐらいかなぁ…。機能の割に高く付きました。
ほとんど使わないまま死蔵する羽目に…。
|
|