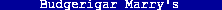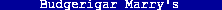| |
▼ようさんさん:
>ところで..以前に「ジェネレーターコイルの良否」で..
>「コイルの1A程度の電流を流して計測すれば分かる」ってことでしたが、
>これのやり方を教えてもらえませんか。(-O-)/
簡単に説明すると、ケルビン法で測定するだけです。
未知の抵抗R[Ω]に既知の電流値I[A]を流すと、抵抗の両端にはE[V]が発生します。
これを利用します。
オームの法則を思い出してください。
E=IR
です。
さて、ジェネレータには二つのコイルがあります。フィールド・コイルとステータ・コイルです。
フィールド・コイルの抵抗値は(純正サービスマニュアルには記載がありませんが)約4.0Ωです。12Vをかけると約3A流れます。
ステータ・コイルの抵抗値は(純正サービスマニュアルによれば)三相の各相とも、0.41〜0.51Ωです。
http://www.engineers-net.com/x/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=70;id=CB750F2
フィールド・コイルの抵抗値は、アナログ・テスターやデジタル・テスター(DMM:Digital Multi-Meter)でも、精度は悪いながら、まぁどうにか測れるでしょう。
しかし、ステータス・コイルの抵抗値は、1Ωに満たないので、テスター棒の
接触が悪かったり、端子が酸化していたりすると測定値がふらつきますし、
デジタルテスターの抵抗レンジは1Ω以下のような低抵抗だと、テスターリード(電線)の抵抗値を測っているのか、被測定物の抵抗を測っているのか定かでなくなります。
アナログ・テスターだと×1Ωレンジでフルスケールを校正してから、測定しますが、
それとても同様な症状で、信憑性の高い測定値を得るのに苦労します。
1枚目の図は2端子法で抵抗値を測る例です。
未知の抵抗Rxを測るのにp点とq点にテスターリードを当てれば、接触抵抗や
テスターリードの抵抗値を無視できます。
2枚目の図を見てください。Rpはa点〜p点のテスターリードや接触抵抗の合成抵抗、
Rqはb点〜q点のテスターリードや接触抵抗の合成抵抗です。
2端子法では、現実にはRpやRqを含めて測ることしかできません。
RpやRqがRxより十分小さければ無視できますが、Rxが0.4Ωしかないのに、
RpやRqが0.2Ωとか、あるいはテスター棒の先の接触具合でふらついたりしたら、
正確に測れませんよね?
これらが低抵抗を正確に測定できない理由です。
ケルビン法では、測定リード線やテスター棒の接触抵抗を無視できるよう
4端子法で測定します。
3枚目の図においてRxが測定したい未知の抵抗で、各端子は次のとおりです。
Ia:電流端子a
Ib:電流端子b
Va:電圧端子a
Vb:電流端子b
p:抵抗器の端子
q:抵抗器の端子
Ia〜Ib端子間に既知の電流Iを流し、Va〜Vb端子の間の電圧Vを測ります。
すると未知の抵抗値Rxは、
Rx=V÷I
から、簡単に求められます。このときRpやRqがRxに比べて大きくても小さくても、
Va〜Vb間の電圧は変わりません。
さて、私たちがステータ・コイルの抵抗値を実際に測定する場合、いちいち
4端子法の計器を購入しなければならないわけではありません。
また、4端子法の測定環境を用意するのはめんどうです。
そこで手っ取り早く、ステータ・コイルの1相に既知の電流として1.0Aを流します。
そしてそのコイルの両端電圧をDMMやテスターで測定します。測定値が0.41Vで
あれば、抵抗値は0.41Ωです。
こうすれば、テスターリードの抵抗値やテスター棒の接触抵抗を無視して、
低抵抗を測定できるわけです。
もうお気づきかと思いますが、既知の電流は1.0Aでなくともかまいません。
電流値が必要十分なだけ正確かつ既知ならば、他の値でもかまいません。
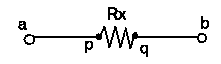
【2terminal-connection.gif : 1.3KB】
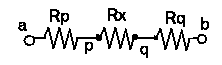
【2terminal-connection2.gif : 1.6KB】
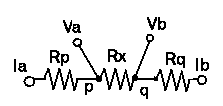
【kelvin-connection2.gif : 1.9KB】
|
|